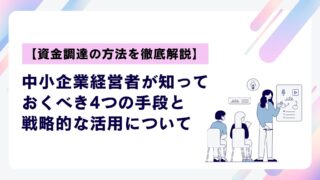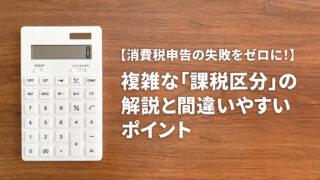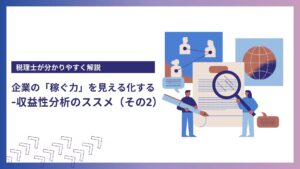【経営コンサルタントが解説】変動費と固定費の違いとは?粗利益で固定費を賄う仕組み

皆さんこんにちは。福岡の税理士 河上康洋です。
私は税理士と中小企業診断士のダブルライセンスを活かして「社長を数字に強くする」セミナーや情報発信をしています。
税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化と、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしてきました。
このコラムでは企業経営者様に向けて実務で役立つ知識をお伝えしています。
今回は変動費と固定費の違い、そして企業が利益を出すための絶対条件についてご説明したいと思います。
経営において大切なこと
企業経営において、「変動費」と「固定費」を正しく理解することはとても大切です。
この2つの費用の違いを知り、どのように利益を生み出すか?を把握することで、経営判断の精度は大きく向上します。
本記事では、変動費と固定費の基本をわかりやすく解説し、最終的に「粗利益で固定費を賄う」という考え方の重要性をお伝えします。
変動費とは

変動費とは、操業度の増減に応じて増えたり減ったりする費用のことです。
例えば、
- 製造業であれば原材料費
- 販売業であれば仕入原価
などがこれに当たります。
変動費の例
- 商品1個を作るのに必要な原材料費
- 売れた分だけ発生する販売手数料
- 配送料
つまり、操業度がゼロであれば変動費もゼロになります。
固定費とは

固定費とは、操業度に関わらず毎月一定額かかる費用です。
代表的なものとしては、
- 事務所家賃
- 人件費(一定給の社員給与など)
- 減価償却費
- 保険料
があります。
POINT
これらは操業度がゼロでも必ず発生するため、経営の安定には固定費をどう賄うか?が重要なポイントとなります。
【図解で説明】変動費と固定費のイメージ


この図は、操業度が増えると変動費が比例して増える様子と、固定費は売上に関わらず一定であることを示しています。
粗利益とは?

TKC出版「経営者のための会計力」より引用
「変動費」と「固定費」を正しく理解するうえで大切なのが「粗利益(限界利益)」です。
粗利益とは、
売上高-変動費(売上原価)=粗利益(限界利益)
粗利益(限界利益)-固定費=経常利益
で計算されます。
つまり、売上から変動費を引いた残りが粗利益です。
この粗利益で、固定費を賄い、その残りが営業利益や最終的な純利益になります。
企業が利益を出すための絶対条件
変動費・固定費を見てきましたが企業が利益を出すためには、粗利益が固定費を上回ることが絶対条件です。
粗利益が固定費を下回っていれば、売上があっても赤字です。
そのために
- 販売単価の設定
- 仕入や原価の管理
- 固定費の適正化
といったポイントを常に見直し、「粗利益で固定費を十分に賄える体質」をつくることが大切です。
変動費と固定費の考え方を理解し、粗利益の大切さを意識することで、経営はより健全になります。
売上だけに目を向けるのではなく、「粗利益で固定費を賄い、利益を確保する」という基本をぜひ意識してみてください。
福岡市・博多エリアの税理士をお探しの方へ

当事務所では「中小企業診断士」の国家資格を持つ経営コンサルタントが会社の強みを分析し、数値化・言語化を行います。
税理士と中小企業診断士の両方の知識を活かし、収益性分析から経営改善提案までサポートしています。
御社の規模・課題に応じて最適なご提案をいたしますので、ご希望の方はお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
河上康洋税理士事務所
代表 河上康洋
プロフィール

- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。